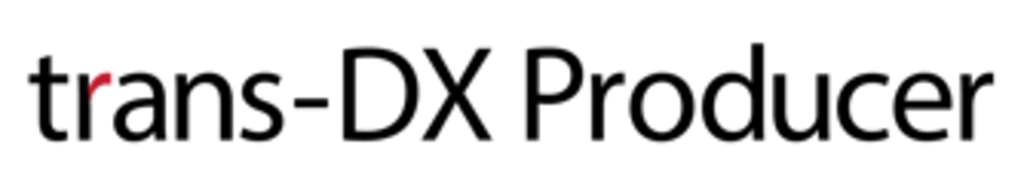trans-DXプロデューサーが切り拓く新たなDX支援の未来
trans-DXプロデューサーは企業が抱える課題に対し、総合的かつ実行力のある支援を提供することを目的としています。
本記事では、制度設立の背景や、業界知見を活かした支援の重要性、そしてこれからのビジネス環境においてtrans-DXプロデューサーが果たす役割について、trans-DX戦略担当役員 小林克成と、trans-DXプロデューサーとしても実際に活動しているCX事業推進本部 副本部長 山田真士がDX支援の未来について語ります。
お客様企業のニーズの変化と総合的な解決策の必要性
---- trans-DXプロデューサー制度設立の経緯と、ここ数年でのお客様企業の課題、求められるサービスの変化などについて教えてください。
小林
トランスコスモスはコンタクトセンター(コールセンター)・Webサイト制作・デジタルプロモーション・ECなどを始め、幅広いサービスを提供してきました。
ただ、昨今のDX市場拡大の流れで、お客様企業も単一のサービスのみをご希望いただくのではなく、お客様企業の持つ課題に対して “総合的に改善していく” といったトータル提案を望まれるケースが多くなってきました。これはサービスの提案に限ったことではなく、トータルでプロジェクトを進めていく部署や人材、いわゆるプロジェクトマネージャーがこれまで以上に求められるようになったという市場の背景やニーズがあり、それらを総合的に提案・サポートしていくための取り組みをとして “trans-DX” を2022年頃から推進してきました。

trans-DX推進担当 常務執行役員 小林 克成
山田
プロジェクトマネージャーという存在に対するニーズは明らかに増えており、年々増加の一途を辿っています。その理由を考えてみると、企業と消費者の接点、コミュニケーションチャネルがものすごく増えてきて、そのなかで取得できるデータも膨大になっていて、でもその膨大なデータを社内で扱える人がいない、このような悩みを抱える企業が増え続けているからなのだと思います。
このような中で、トランスコスモスはお客様企業に何を提供できるだろうと考えたとき、単体のソリューションを提供するのではなく、チャネルを横断してお客様企業が持つデータを分析・活用し、課題解決に役立てる。そしてそれを実行するための人材までをセットにして、1つのサービスとして提供する。ここまでして初めて市場のニーズに応えることができるだろうという結論に至りました。

CX事業推進本部 副本部長 兼 trans-DXプロデューサー 山田真士
---- そのような背景から、trans-DXプロデューサーという存在が必要になったのですね。trans-DXプロデューサーとは具体的にどのような人材なのでしょうか?
山田
プロジェクトマネージャーは、プロジェクト単位で、縦割りにそれぞれ配属されている責任者というのが一般的なイメージかと思います。
例えば、Webサイト制作・リニューアルというプロジェクトがあったとして、プロジェクトマネージャーはせいぜいフロントエンドとバックエンドを横断するくらいで、Webサイト制作・リニューアルに付随するその他のプロジェクトまでを見ることはほとんどありません。
一方、trans-DXプロデューサーはプロジェクト単位で物事を見るのではなく、Webサイト制作・リニューアル / コンタクトセンター運用 / SNS運用 / アプリ開発・運用 / 広告配信 / 各種タッチポイントから得られたログデータとそれに紐づく部門の方たちとのコミュニケーションなど、対応範囲をあげはじめたらキリがありませんが、これら全てを包括的に、横断してプロデュースします。
---- 一般的なプロジェクトマネージャーと比べて、対応する領域の広さと業務量が全然違うのですね…! ただ、これっていわゆるコンサルタントとは何が違うのでしょうか?
山田
一般的なコンサルタントとの違いは、先ほども少しご紹介しましたが、とにかく「対応領域の広さ」と「実行力」です。
例えば、コンサル企業が2つの部門を跨いだ改善案などの全体フレームを書いたとして、それを実際に実行するのはお客様企業の現場です。とすると、現場の人たちが業務に落とし込んでPDCAを回せるようにするには、そのフレームにあわせて業務プロセスも書き直す必要が出てきます。加えて、2つの部門を横断した業務プロセスを設計するには、2つの部門それぞれの業務特性などを理解している必要もあります。
では、コンサル企業がコンタクトセンター領域の知見と、マーケティング領域の知見どちらも持っているのか?というと、恐らくそうではないケースがほとんどだと思いますし、現場の運用までを含めてトータルでサポートするとなると、trans-DXプロデューサーは唯一無二の存在といっても過言ではないと思います。
絵に描いた餅で終わらせずに、実行するところまでしっかりと共にやりきる。やりきらないと、お客様企業のKPIに貢献できない。この信念をもってプロデュースするというところが、一般的なコンサルタントとの大きな違いではないでしょうか。
業界知見の活用:トランスコスモスが提供する多面的な支援
----trans-DXプロデューサー制度について、2024年11月に開催されたトランスコスモスフォーラム2024(CXパート)で正式に発表したわけですが、お客様企業からどのような反応があったか教えてください。
小林
trans-DXプロデューサーについて、FOOD & LIFE COMPANIES様、りそな銀行様、みずほ銀行様、日本航空様、での事例をお話しさせていただきました。これまでのお客様企業とトランスコスモスとの接点を振り返ると、コンタクトセンター、Webサイト制作、EC、とそれぞれ縦割りでのサービス提供をご希望いただいてきましたし、そこに期待感を持ってご指名いただくことが多かったのですが、trans-DXプロデューサー制度の本格始動を発表したことで、これまで以上にお客様企業のデジタル・DX支援をすることができると多くの方々へ知っていただくことができました。
結果として、各業界のお客様企業から数多くのDX推進に関するご相談をいただくこととなり、想像以上の反響をいただけたことは素直に喜ばしいですし、同時にお客様企業から寄せられた期待感にお応えするためにも、そしてさらに各業界の課題を深く理解するためにも、業界別のtrans-DXプロデューサーを編成し、業界知見を活かした提案を行うことでBX(ビジネス・トランスフォーメーション)まで提言できるような活動、支援を進めています。
山田
日々、お客様企業からいただく反応で面白いと感じるのは、これまでのトランスコスモスのケイパビリティにない領域のご相談もしていただけるようになったことですね。
例えば大手飲食チェーン様では、現場が抱えている業務課題が店舗の裏側である調理オペレーションにあって、そこもある程度は自動化されているけど、まだまだ人が介入していてDX化が思うように進んでいない。加えて、フロント側はアプリ / LINE / Webサイトなどからログデータが大量に取れていますが、バックヤードについてはまだまだデータが足りない。なので、「バックヤード領域のデジタル化を是非提案してほしいから、一度店舗の裏側の実態を知ってもらうためにも調理オペレーションを体験してほしい」とのことで、実際に店舗で調理工程を体験してみて、課題に感じる部分などについてレポートをあげてほしいと依頼されています。このような経験ができるのも、trans-DXプロデューサーとしてお客様企業からトータルでの提案・改善にご期待いただいているからこそですよね。
---- お客様企業から、スピード感と実行力を求められているのがよく分かりますね。 トランスコスモスが提供するDX推進の支援において、trans-DXプロデューサーが果たす役割や、その重要性について具体的に教えてください。
小林
トランスコスモスはエンタープライズ企業、かつ業界のTOP10のお客様企業とお取り引きさせていただいていますから、トップ企業のDXの取り組みや、業界別にお客様企業が抱える課題と改善策などの成果や知見を蓄積し、それをナレッジ化できています。そのため、トランスコスモスへDX推進についてご相談いただいた際は、個社の課題だけでなく、業界特有の課題などについてもナレッジ化したデータをもとにご提案することができます。
また、お客様企業が同業他社との差別化を図るうえで、全く異なる業界の知見なども取り入れて進化していくことも重要だと考えています。そういった意味でも、流通 / 製造 / 金融 / 小売 / インフラ / マスコミ / 情報・通信 / 自治体など、多岐にわたる業界の知見を持っているトランスコスモスが第三者としてプロデュースし、日々の業務に落とし込みながら支援できることは強みでもありますし、お客様企業と一緒にBXに向けて取り組んでいく人材になることが、すべてのtrans-DXプロデューサーが目指すべき姿でもあると思っています。
山田
トランスコスモスがお客様企業のビジネスを支援する・共に取り組むことの意義、そしてお客様企業から求められていることは、ひとえに “業界知見の活用” に尽きると思っています。
トランスコスモスがこれまでご支援してきた課題と改善策について、「業界別にデータベース化して、〇〇業界で多い課題にはこんな傾向があって、そのためのアプローチはこんな方法がある」というようなデータをもとにした会話ができるようになっていくことで、お客様企業がこれまで持っていなかった考え方や知見を落とし込めるようになる。社外の “trans-DXプロデューサー” という存在を入れたことによって、社内のデータサイエンティストだけでは見えなかった物事が見えてくる。それを経て、冒頭にもあった事業設計やビジネス設計に関する議論を深めていく。この流れを作っていくことがtrans-DXプロデューサーの使命だと思っています。
進化を続けるtrans-DXプロデューサーの役割と今後の展望
---- 最後に、trans-DXプロデューサーの今後の展望などを教えてください。
小林
中期経営計画としては、trans-DXプロデューサー100名、取引企業500社を目指しています。そのためにも、trans-DXプロデューサーは業界業務に精通し、お客様企業が持つ課題や取り組むべき方向性を先回りして示唆・解決できるよう、DXに関する知見はもちろんのこと、事業のサポート役として相応しい知識の習得、AI活用スキルの習熟と、ビジネス・テクノロジー両面での向上を行なっていきます。
山田
あとは、生成AIを活用した取り組みについても強化していきたいですね。チャネル横断での改善をしていくうえで、いまはどうしても各業務の可視化をするプロセスを人力で進めることが多いんです。人力で業務ヒアリングをして、業務プロセスを作成して、ローンチ後のプロセスも人力で運用する。
今はこのプロセスに対し、徐々にAIを用いた効率化を進めていて、例えばLPを自動生成してこれまでは1週間かかっていた制作物を5~6時間ほどで形にする。そしてそれを見越して業務BPRを作っていくことで、例えば広告とアプリを連動させたPDCAをこれまでは1カ月単位で回していたところ、1週間でできるようになったという事例も出てき始めています。
これまでは「生成AIを使って何ができるだろう?」と考えるところからスタートしていたものが、trans-DXプロデューサーが業務プロセスを可視化し、BPRを進めていくなかで、自然と生成AIを用いた省力化・自動化・標準化も検討されるようになります。そのため、現場に根ざした効果のある取り組みができています。
---- なるほど、社内にプロンプトをかける人はいても、そのプロンプトを業務に落とし込める人がいないというケースもよく耳にしますが、trans-DXプロデューサーが支援することでそれを防げるわけですね。
小林
加えて、中国やインドなどの海外拠点を持つトランスコスモスは常に生成AIをはじめとする最先端テクノロジーが入ってくる環境にあるので、お客様企業の課題にあわせて、いち早く海外の新しい技術を提案・実行できるというアドバンテージもあります。これを活かして、trans-DXプロデューサーが中心となって、お客様企業とともに新たなことにも積極的にチャレンジいきたいですね。
---- まだまだtrans-DXプロデューサーの進化は止まらないということですね。 本日はありがとうございました。

<参考>trans-DXプロデューサーとは