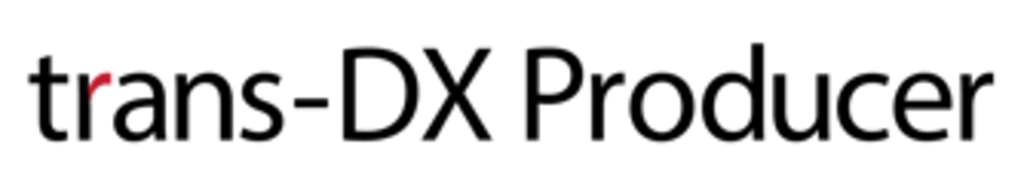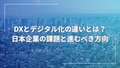CXとは何か?顧客体験がビジネスの成否を左右する理由と向上のヒント
近年、ビジネスの成功においてCXの重要性はますます注目されています。
消費者(顧客)が「このブランドから買ってよかった」「また利用したい」と感じる瞬間を積み重ねることが、競争が激化する現代の市場で持続的な成長を支える鍵となっています。ポジティブな体験はリピーターや新規顧客を増やし、逆にネガティブな体験は離脱を招く可能性があります。
本記事では、CXの基本からその向上方法までを分かりやすくお伝えします。
CX(カスタマーエクスペリエンス)とは?
CX(Customer Experience/カスタマーエクスペリエンス)とは消費者が製品やサービスを利用する際に得られる体験全般を指し、その範囲は単なる購入プロセスに限らず、広告との接触、問い合わせ、SNSでの投稿閲覧、アフターサポートなど、カスタマージャーニー全体を通じて蓄積されるものです。
CXと似た言葉にUX(ユーザーエクスペリエンス)がありますが、UXは「製品やサービスの使いやすさ・使い心地」に特化した体験を指すのに対し、CXはその前後も含む、もっと広い視点での体験を扱います。
たとえば、Webサイトでの購入体験(=UX)も重要ですが、購入前の広告との出会いや購入後のサポート体験(=CX)が悪ければ、全体の評価は下がります。
なぜCXが重要なのか?
現代の消費者はモノやサービスの質だけでなく「どのような体験ができるか」を重視しています。
良好なCXを提供できれば、CS(顧客満足度)や、ロイヤルティ(再購入意欲、推奨意欲)が向上し、結果としてLTV(顧客生涯価値)が高まります。反対に、CXが低ければ競合他社に簡単にシェアを奪われてしまいます。
良好なCXとは、消費者が製品やサービスを利用する際の利便性や満足度が高い状態を意味します。例えば、直感的で使いやすい製品設計、明確で分かりやすい情報提供、スムーズな購入プロセスがあるなどです。
良好なCXを提供することで消費者がブランドのファンになり、自発的にSNSで好意的な投稿をする、口コミで拡散する、などのほか、カスタマーサポートの負担が減ることが想定されます。
また、良好なCXには明確なFAQ(よくある質問)やセルフサービスツールの提供が含まれ、信頼されているブランドの場合、消費者はブランドや製品に対してポジティブな感情を持つことが多く、即座にカスタマーサポートに連絡する代わりに、自身で解決しようとすることがあります。 これにより、カスタマーサポートの時間やリソースの節約にもつながります。
一方で、CXが悪いと苦情や悪評がSNSや口コミサイトで拡散される、カスタマーサポートコストが増大する、離脱率や解約率が上昇するなど、企業の業績や評判への悪影響が予想されます。特にBtoCビジネスでは、1人の消費者の不満がネット上で瞬時に共有され、企業の信頼を損なうリスクがあるため、CXへの配慮は不可欠です。
CX低下によるリスク(一例)
リスクカテゴリ | 具体的なリスク | 影響 |
CSの低下 | ・消費者の不満足感が増加する | ・ブランドイメージの悪化 |
消費者の離脱 | ・消費者が競合他社に流れる | ・売上減少 |
カスタマーサポートの負担増加 | ・問い合わせやクレーム対応の件数増加 | ・サポートチームのリソース不足 |
口コミ・評判の悪化 | ・ネガティブな口コミが広がる | ・新規顧客獲得が難しくなる |
売上への影響 | ・リピーター数の減少 | ・短期的、長期的な収益の減少 |
競争力の低下 | ・競合他社に市場シェアを奪われる | ・差別化要因の喪失 |
法的リスク | ・消費者からの不満が訴訟に発展する可能性がある | ・訴訟対応コストの発生 |
従業員への影響 | ・従業員のモチベーションが低下 | ・離職率の増加 |
長期的なブランド価値の低下 | ・信頼を失い、ブランド価値が毀損される | ・競争優位性の喪失 |
新規顧客の獲得困難 | ・悪い評判が新規顧客獲得を妨げる | ・市場拡大の停滞 |
CXを向上させるために必要なこと
まず重要なのは、自社にとってのCXとは何かを定義し、可視化することです。
一口に「CX」といっても、「感動的な体験」や「一貫性のあるシームレスな体験」「情緒的な価値の提供」など様々な視点で語ることができ、また自社がおかれている状況や業種・業界によっても取り組むべき内容の優先度は異なります。まずはCXやCSを改善することで、企業の収益性を向上できるかに焦点を当て、取り組むのも良いでしょう。
また、日本企業はアメリカの企業と比べ、CX領域におけるAI活用・自動化など最新技術を用いた取り組みと、データに基づいた取り組みが大きく遅れていることも分かっています。ただなんとなくあてずっぽうで取り組んでも当然、良い結果は得られません。CXを本気で改善するにはまずは解決すべき課題が何かを具体化し、改善すべき指標を定義したうえでそれを測定し、データに基づいて取り組みを進める必要があります。
CXの善し悪しを指標を用いて測定する際、代表的なCX指標としてNPS®・CSATを利用するケースが多く見られますが、いずれも万能ではありません。トランスコスモスでは、コールセンターやWebサイトなどのタッチポイントの運用改善や、カスタマーサポートの満足度向上を目的とする場合は、コミュニケーション領域に特化した指標である「コミュニケーション体験評価(COMX)」を活用することをお勧めしています。
COMXの具体的な解説は以下の記事からご覧いただけます。
<参考>
コミュニケーション体験の評価とは?CX向上のための分析手法を解説
CX改善の極意は「守・破・離」 顧客体験を革新するための秘訣とは
トランスコスモスが提供するCX向上のトータル支援
トランスコスモスはWebサイト、チャット、コールセンター(コンタクトセンター)、SNSなど複数チャネルを横断した運用・データ活用によりCX向上、売上拡大に貢献します。
【対応範囲(一例)】
■Webサイト・アプリ構築/運用
消費者はWebサイトやアプリを通じて、企業へ問い合わせをします。顧客接点の起点となるWeb広告、Webサイト構築を、年間600社を超える豊富な実績とノウハウをもとに、最適な導線設計、コンテンツの企画・制作を実施します。
・サイト運用・改善サービス
・マーケティングソリューション導入サービス
・システム構築/開発・インフラ保守
■チャットボット
チャットボットを導入することで24時間・365日対応可能なコールセンター(コンタクトセンター)を実現。有人チャットと連携することで、CX向上と自己解決率向上を実現します。
・チャットボットの設計や運用チューニングには、Webサイト診断サービス、FAQコンサルティングサービスのノウハウを活用
・FAQコンサルティングサービスでは、経験豊富なAIストラテジスト100名が、コールやメールのログから顧客の求める回答や説明のレベルを抽出し、自己解決を促進
・FAQサイトの現状をコンテンツカバー率で把握したうえで、FAQ整備からbotの設計開発までをワンストップで提供
■チャットオペレーション
電話同様リアルタイムでの対応を可能にするチャットオペレーション。テキストでのやり取りだけでなく画像活用も可能なことから、お問い合わせの敷居を下げます。1人のオペレーターでも複数人の顧客を同時対応できるため、入電集中の回避や関連資料送付による、業務効率改善も支援します。
・ノンボイスセンター(チャット)国内1,000席稼働中
・チャットオペレーション実務能力認定構築
■デジタルコールセンター(コンタクトセンター)
コンタクトセンター運営に必要なさまざまなチャネル(コール/メール/LINE/チャット/SMS/リモート/FAX/DM/訪問)に対応したテクノロジーの導入・運用をサポートし業務の効率化と最適なコミュニケーションを生み出し顧客とのエンゲージメントを構築します。
・国内32拠点18,380席 海外45拠点15,810席のセンター稼働中。在宅オペレーターにて国内1,000席 海外3,000席稼働中 ※2021年12月時点
・コールセンターの対話ログの音声認識ソリューション「transpeech2.0」を提供
■ソーシャルリスニング
消費者は企業の応対や商品についてSNSに投稿し、SNS内で情報検索を行うなどSNSを通じて購買意欲を高める体験をしています。これらの消費者が発するSNS上の声を収集・分析し、サイレントマジョリティの不満や疑問だけでなく、ポジティブな評価やニュートラルな声も分析することで、各チャネルのコンテンツ改善から広告の訴求開発、ESの向上まで幅広く活用します。
・Twitterキャンペーンからその他ソーシャルメディアまで多様なセンター運用が可能。複数のソーシャルメディアの運用監視オペレーションを24時間365日で実現
・ソーシャルリスニングによるVOCをポジティプ・ネガティブ・ニュートラルに分類。区分を明確化し、デジタル広告展開
カスタマージャーニーに沿った一連のプロセスを、チャネルごとではなく総合的に管理することで定量・定性的に課題を可視化し、PDCAモデルを構築・運用できる唯一のパートナーとして、お客様企業のDX推進を支援しています。
まとめ
良好なCXを通じてブランド価値を高め、ファンを生み出し、消費者との長期的な関係を築くことで、競争激化する市場での成長を支える基盤を構築することができます。企業にとって、CX改善は単なる選択肢ではなく、持続可能な成功のための必須戦略と言えるでしょう。
トランスコスモスは、CX向上を通じてお客様企業と消費者の未来をつなぐパートナーとして、戦略から運用まで一気通貫でご支援しています。ぜひ一度ご相談ください。
関連情報
trans-DXプロデューサーとは