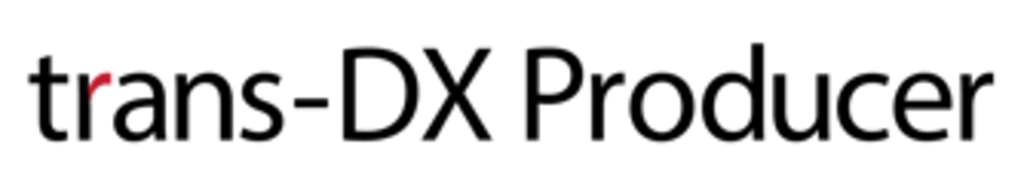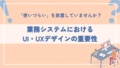DX推進に必要なデジタル思考 変革を成功させる「意識」と「実践」のポイント
DX推進とは単なるデジタルツールの導入やシステム刷新だけではなく、“デジタル思考” や “部門横断型の旗振り役” を軸としたマインドセットの醸成と実践が不可欠です。
デジタル思考とはデータを基に現状を客観的に分析し、柔軟かつ合理的な意思決定を行うアプローチです。企業のDX推進を担う担当者・マネジメント層・WEB設計者の方は、自社のビジョンを明確にし、従来の成功体験や既存プロセスから一歩踏み出し、デジタルがもたらす可能性に目を向けることがDX加速のカギとなります。
そこで本記事では、DX推進におけるデジタル思考の重要性と、それを支えるマインドセットについて詳しく解説します。変化の激しいビジネス環境において、自社のDXをどのように加速させていくか一緒に考えてみましょう。
DX推進における “デジタル思考” の重要性
企業や組織でDXが叫ばれて久しい現在、単なるIT導入や業務効率化にとどまらず事業モデル自体の変革が本格的に求められています。
しかし、多くの現場で「DXがなかなか定着しない」「成果に結びつかない」といった悩みが依然として多く聞かれます。この背景にあるのは単なるデジタル技術の導入ではなく、ビジネス全体を再設計する “デジタル思考” を基にした根本的な意識改革の欠如です。
いまやDXという言葉自体は多くの人々に浸透していますが、ビジネスの現場では「なぜDXが必要なのか」「どのような意識で取り組むべきなのか」という本質的な問いが十分に共有されていないことがしばしば見受けられます。
デジタル思考とは単なる道具としてのデジタルツールを使いこなす発想ではなく、ITやデータを活用し現状を客観視・分析し、合理的かつ柔軟な意思決定や業務設計を行うことで、従来のビジネスプロセスや組織構造の枠組みを根本から見直し “顧客価値を最大化できるように、デジタルやデータを用いて全体最適を図るための思考” です。
DXを推進した先に目指すゴールは、ビジネスモデルや業務の変革を通じて、社会や市場の激しい変化に迅速かつ柔軟に対応できる組織へと生まれ変わることにあります。デジタル技術はもちろん重要ですが、大切なのは「何のためにデジタルを活用するのか」の目的意識です。特に、経営層から現場の担当者まで全社的にこの意識が共有されているかどうかが、DXの成否を大きく左右するといえるでしょう。
以下にデジタル思考を身につけることで得られるメリットをいくつかまとめました。
デジタル思考を身につけることの重要性
迅速な意思決定を可能にする
デジタル思考を持つことで企業はデータをリアルタイムで分析し、迅速な意思決定を行うことができます。たとえば、消費者の購買データや市場の動向を分析することでどの製品を強化すべきか、どのタイミングでキャンペーンを行うべきかを判断できます。これにより、競争力を維持・向上させることができます。
消費者(顧客)中心のアプローチを実現する
デジタル思考では消費者の意見やフィードバックを重視します。SNSやオンラインレビューなどさまざまな情報源から消費者の声を集め、それを基にサービスや製品を改善することが可能です。これにより消費者のニーズに合ったサービスを提供し、満足度を高めることができます。
チームの協力と柔軟性を向上する
デジタル思考を持つチームは情報共有がスムーズで、異なる分野の専門家からの協力を得やすくなります。例えば、マーケティングチームとIT部門が連携してデジタルキャンペーンを展開することで、より効果的な結果が得られます。また、変化する市場環境に対して柔軟に対応できるため、組織全体の適応力が向上します。
デジタル思考を支える4つの視点
DX推進に必要なデジタル思考は、いくつかの視点に分けて整理することで理解しやすくなります。ここでは企業のDX成功事例や業界専門家の知見をもとに、特に本質的な4つの視点を抽出します。
消費者(顧客)中心の発想
まず重要なのが、消費者を中心とした発想です。DXの根底には従来型の「自社都合」ではなく「消費者が本当に求める価値とは何か」を徹底的に考える姿勢が欠かせません。
消費者の課題や行動を定量・定性の双方からデータで把握し、サービスやプロセスを再設計するなど、単なる効率化で終わらせず市場の信頼を勝ち取るためには、この発想が不可欠です。
たとえば大手流通業では店舗とECの両方で取得した消費者のデータを分析し、一人ひとりに最適化したサービスを提供することで飛躍的な業績向上を実現しています。これが実現できたのは、「消費者起点」の徹底があったからです。
全体最適×ボトムアップ
DXには「部分最適」ではなく「全体最適」が求められます。現場ごとに異なるシステムやプロセスを維持するのではなく、部門横断的な視点で業務フローやデータ構造を見直す必要があります。加えて、現場からの意見や知恵を柔軟に吸い上げるボトムアップの姿勢がDXの定着には不可欠です。
成功企業の多くは、経営層がビジョンを提示しつつも、現場主導で日々の改善や新規施策を推進しています。現場目線と経営目線の融合が、デジタル時代の組織に求められる姿です。
迅速なPDCAと失敗許容
DXは「やってみてから」考えることが重要です。長期間の検討の末に完璧なものを目指すのではなく、高速でPDCAサイクルを回し、失敗を経験としながら最適解へ近づける。それがデジタル時代の正しい歩み方です。
逆に失敗を恐れて何も実行できない組織は、市場のスピードについていくことができません。ITベンチャーをはじめ既存大企業でも、早期から「まず動かしてみる」思考を重視する例が増えています。
データドリブンな意思決定
最後に、「データに基づく意思決定」がデジタル思考の土台となります。従来の経験や勘に頼った判断から脱却し、膨大なデータやAI解析結果を活用して最善策を導き出す、このマインドセットの転換が現場ごとに徹底されれば、組織全体の意思決定の質が劇的に向上します。
たとえば製造業の事例では、不良品発生時の現場レポートだけでなく、センサーやIoT機器から取得した大量データをAIで分析することで、わずかな異常値の予兆を事前に発見し、損失の大幅削減に成功しています。
このように、従来のビジネスの現場で根強く残る “現状維持志向” や “過去の成功体験に基づいた意思決定” といった思考スタイルだけでは、デジタル技術の急速な進化や消費行動の変化、市場競争の激化に対し柔軟に対応しきれず、改革が遅れる大きな要因となります。
まずはDX推進を成功させるために、以下のようなマインドセットを意識してみましょう。
・変化を受け入れ “やってみる” 姿勢
・データや事実に基づいた意思決定
・部門や役職、組織の垣根を越えた協働意識
・顧客価値の最大化・消費者起点での思考
・「失敗から学ぶ」プロトタイピングとフィードバック文化
デジタル思考が業務・ビジネスに与える好影響
実際にDXで成果を上げた企業は、デジタル思考をどのように現場で体現しているのでしょうか。ここでは複数業界の実例から共通する「思考と行動」を紐解きます。
製造業の切り口 AI・IoT活用と現場改善
従来、職人技や人の勘に依存していた製造業において、生産ラインの最適化を目指し高度なAIとIoTが導入されたことで現場ではセンサーから24時間リアルタイムで情報を収集。それをもとにAIが生産スケジュールや保全計画を自動提案するといったように、劇的にDX化が進んでいます。
ここで重要なのは「AIを活用する目的」を徹底的に議論し、作業員自身が新しい技術の使い方や生産効率化施策を現場改善活動に取り入れた点です。「自分たちが変わる」「納得して使う」意識が現場に根付いたことで、全社的な生産性と安全性の向上が達成できたのです。
小売・流通の切り口 データ共通基盤と顧客価値最大化
小売・流通業界では、複数チャネル(リアル店舗・EC・アプリ)間で分断していた消費者の情報や、販促施策のデータ共通基盤を一新するなど、各部門ごとの局所最適から「データにもとづく全体最適」への転換が進んでいます。
また、CXの最大化を目指し、AIによるレコメンドやパーソナライズ、リアルタイム在庫連携などの導入が進み、結果として売上増だけでなくファンの継続率も向上しています。これは「消費者起点」「ボトムアップ」「データドリブン」というデジタル思考が現場で一体となって機能することで初めて実現することができます。
金融業界とパブリックセクター リスク管理と業務最適化
DXが求められるのは民間企業だけではありません。金融業界や公共機関でも、膨大な取引データ・システム老朽化・対外的責任など複雑な課題が山積しています。
金融業界ではリスク管理と不正検知の強化にAI・データ分析を導入することで現場のオペレーション効率だけでなく、新たなサービスや商品開発のヒントを “データ起点” で生み出し、公共団体においても業務効率化や住民サービス向上のため全体最適設計ができる人材チームを新たに編成し、きめ細やかな業務フロー設計と意識改革を進める取り組みが活発化しています。
デジタル思考が醸成されると、属人的なノウハウや経験則頼みの業務から脱却し、データ・プロセス中心の業務設計が実現します。これにより特定の担当者がいないと業務が回らないといったリスクが減り、生産性向上やクオリティ担保が期待できます。
変化の激しい市場環境下では、迅速かつ柔軟な意思決定が求められます。デジタル思考は「現状分析→仮説の設定→検証(実行)→改善」のサイクルを高速化し、従来の経験則に頼る意思決定から脱却。事実とデータをベースにスピーディな施策展開を可能にします。
自社DX推進・DX人材育成のためのヒント
全社的な変革は大きな負荷を伴いますが、いきなり壮大なプロジェクトを始めるのではなく、現場主導で「課題の見える化→小さな改善→成果の共有・横展開」という、小さな循環を回し続けることが鍵となります。成功体験の積み重ねがマインド変革やデジタル思考の自発的な醸成につながります。
DX人材の育成・確保には自社内製化だけでなく、先進事例企業・DX専門会社との連携や越境学習、各種リスキリングプログラムの活用も有効です。現場担当者や若手社員にDX推進の経験・ノウハウを積ませるとともに、IT部門や特定のDX推進部門に留まらず、営業・企画・生産など全社横断的にプロジェクトを推進するプロデューサーの役割に求められる知識と思考を身につけることも重要です。
また、DXを推進するうえで多くの組織が直面するのが「現場の意識の壁」と「プロセスの形だけの形式化」です。
たとえば、
・デジタルの活用目的が現場に伝わっておらず、「自分ごと化」されていない
・部署間の縦割りやシステムの独自運用が改革を阻害している
・「失敗してはいけない」「とりあえず従来手法」という同調圧力が根強い
・「DX=システム導入」と捉えるなど、デジタル化が目的化してしまっている
こうした現状では、たとえ最新のITを導入しても現場文化や業務フローが変わらずDXは形骸化してしまいます。
従業員の意識を変えるヒントは「なぜDXが必要か」を問い続ける姿勢です。ミーティングや朝礼の場で、現場リーダーがDXの意義を繰り返し発信する。実例や数値で成果を見せ、「やれば変わる」という納得感を積みあげる。こうした日々の積み重ねが文化の変容につながっていきます。
とくに現場主導の小さな成功体験を重ねていくことで、自分たちが主役となって変わる意識が醸成されます。経営層の “ビジョン提示” と、現場の “課題解決” の両輪がかみ合うとき、DXは初めて本物になります。
加えて、「デジタル思考」を組織へ浸透させるには具体的な仕組みの設計と風土づくりが重要です。ここでは、多くの企業・団体が実践した主要な方法を整理します。
・DX推進チームによる横断プロジェクト
各部門のデジタル推進リーダーを選出し、横断的なDXプロジェクトチームを設置します。プロジェクトの初期段階で「なぜDXをやるのか」「自分たちの業務がどう変わるのか」を全員で議論することが極めて重要です。全社横断の視点と現場の実情を組み合わせた推進体制が、現場定着の成否を左右します。
・「現場主導」の課題抽出・施策設計
経営層のトップダウンだけでなく、現場から課題を抽出し解決策を提案していくボトムアップ型の体制が求められます。現場でのヒアリングやワークショップ、アイデアソン(集団でのアイデア出し)は、意識変革に有効です。
・PDCAサイクルの高速化と実験文化
PoC(概念実証)から小さく始め、得られた学びを活かして迅速なPDCAを回すプロセスが必要です。半年~1年サイクルの「様子見」ではなく、1か月単位で効果検証を繰り返すと、現場の主体性と学習文化が定着しやすくなります。
・外部パートナーとの連携・人材シェア
先進的な知見や最新技術を持つ外部パートナーとの連携や、人材シェアによる多様な「デジタル思考」のインストールも推奨されます。自組織の常識を打破し、競争優位性を生むヒントとなるためです。
・学習・啓発の場の継続的提供
業務時間中に勉強会やライトニングトーク、失敗談共有の場など学習・気付きを得る仕組みを継続的に設けると、「新しい変化を受け入れる土壌」が育ちます。単発の研修やOJTだけではなく、定期的な組織学習が不可欠です。
トランスコスモスでは『trans-DXプロデューサー』がお客様企業の全社的なDX推進の旗振り役として、部門を跨いで効率的かつ一気通貫で力強くサポートしてます。trans-DXプロデューサーについては以下のリンクから詳細をご確認いただけます。
<参考>trans-DXプロデューサーとは
まとめ:DX推進を加速させるために求められる視点
DXを成功へと導くためには、単なるデジタル技術の導入を超えた “デジタル思考” の全社的な醸成が不可欠です。
消費者を中心とした発想、全体最適を目指す視点、迅速な実験と失敗許容、そしてデータドリブンな意思決定。これらの要素を深く理解し、実際の業務やプロジェクトで体現することで組織は本質的な変革を実現できるでしょう。
現場と経営層が「なぜDXを進めるのか」の目的を見失うことなく、小さな成功体験を積み重ね、自分たちがDXの主役であるという自覚を持つ。一人ひとりがデジタル思考に向き合い、変化を恐れず挑戦し続けることがこれからの時代の持続的成長のカギです。
DX推進の本質は “新たな価値の創造” です。本記事が、より深い意識改革と実践的な変革の一助になれば幸いです。