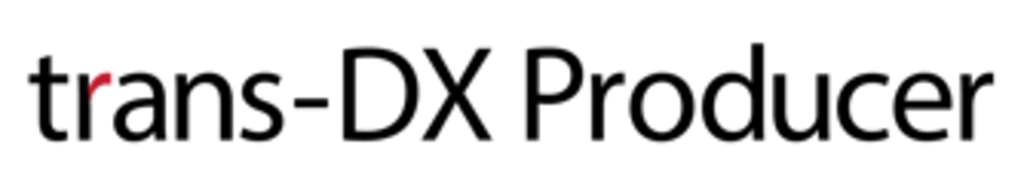RFPとは? 初心者でも分かる提案依頼書の基本と作成手順・活用のコツ
新規システムの導入や業務プロセスの外部委託を検討する際、「RFP(提案依頼書)」という言葉を目にすることも多いのではないでしょうか。
求めているものと異なる成果、期待外れのサービス、ベンダーとの意思疎通のすれ違い、そんな失敗談は多くの場合、要件定義や意図の共有が不十分だったという共通点があります。
しかし、RFPを正しく理解し活用できるようになれば、要求や目標の明確化につながるだけでなく、発注側と受注側の齟齬を回避し、プロジェクト成功率を高めることができます。本記事では、RFPの基礎や作成の流れ、押さえるべきポイントを解説します。
RFP(提案依頼書)とは何か?基本の理解
企業がシステム導入や業務委託など大きな意思決定を行うとき、必要となるのが「要件の明確化」です。この時、多くのプロジェクトで使われるドキュメントが「RFP(Request For Proposal)」日本語で「提案依頼書」と呼ばれるものです。
RFPは「このようなシステムを作りたい」「こういったサービスを提供してほしい」という要件や条件を、発注側(顧客)が受注候補(ベンダー)に文書で提示するものです。目的や課題、期待する成果までを広く・具体的に示し、「こういう提案をしてください」と依頼するのが基本となります。
一般的な発注プロセスでは、このRFPに沿って複数のベンダーが提案内容を競い、その中から最適な提案が選定されます。そのため、RFPが曖昧なまま進めてしまうと要望が意図通り伝わらず、完成品の品質やコスト、納期に大きく影響を及ぼすことも少なくありません。RFPは「プロジェクトの設計図」とも言われるほど重要なものなのです。
RFPが求められる背景と役割
RFPが求められる背景には、業務のIT化・アウトソーシングの進展に加え、「自社の課題を的確に解決できるパートナー選び」の重要性が高まった社会的要請があります。
業務効率化やDX推進を筆頭に、多様なシステム導入やサービス委託が増えている現代。選択肢が広がる一方で、「本当に自社に合った提案」を見極める能力がますます求められています。
RFPの持つ役割は、「自社の真のニーズを正確に言語化し、相手企業にも分かるように伝えること」に尽きます。これにより、候補企業は発注側が何を求めているかを把握しやすくなり、質の高い提案や見積もりが可能となります。
また、複数ベンダーの比較検討や選定プロセスの透明性確保にも貢献し、業務を進める上で発生しやすい “言った・言わない” のリスクを最小化する効果も極めて大きいです。
RFP作成の流れと重要なポイント
RFPを作成するには一定の手順と準備が不可欠です。準備不足のままでは、かえってプロジェクトに混乱を招くこともあるため、確実な段取りが求められます。RFPの作成手順はおおまかに下記の通りです。
1. プロジェクト目的の明確化
2. 現状(As-Is)と理想(To-Be)の整理
3. 必要要件や条件のリスト化
4. 期待する成果・評価基準の明示
5. 情報収集・社内ヒアリング
6. RFPドラフト(案)の作成
7. 関係者でレビュー・修正
8. ベンダーへ提示し、質疑応答に備える
特に重要なポイントは「目的と課題が曖昧なまま進めない」こと。
RFPは単なる“要望の羅列”ではなく、「最終的にどんな成果を得たいか」というゴールから逆算して必要事項を整理するのがポイントです。現状調査やヒアリングを丁寧に行うことで、本当に必要なもの・そうでないものの見極めが可能となります。
さらに、情報を分かりやすく体系立てて整理する必要もあります。専門用語を使う場合は、注釈等で意味を補足するなどしましょう。
RFPに盛り込むべき必須要素
続けて意識すべきなのは、RFPにどのような内容を盛り込むべきかです。
質の高いRFPは発注者の思い込みや抽象的な表現を避け、論理的に構成されています。以下に基本的な記載項目を整理します。
9. プロジェクトの背景と目的
導入や委託の背景「なぜこのプロジェクトが必要か」を記載します。現状の課題を明確にしておくことで、ベンダー側も問題意識を共有しやすくなります。
10. 期待する成果・ゴール
「○○のコスト削減」「××システムの安定稼働」など数値で計れる成果をできる限り明確に示します。抽象的な“効率アップ”ではなく、何を持って成功とするか基準を設けることが重要です。
11. 業務範囲・対象部門
プロジェクトのスコープや対象となる業務、部門範囲を整理し「どこからどこまで」がベンダーに求めるものであるかを明確にします。
12. 必須要件と希望要件
「必ず満たすべきもの」と「可能なら取り入れたいもの」を分けてリスト化します。優先度を明確に表現すれば、不要な見積もりの膨張や、期待外れを防ぐことができます。
13. 現状システムまたは業務の情報
既存システムのスペックや課題、利用しているソフトウェアなど、変更点や引き継ぎ条件も漏れなく記載するのがポイントです。
14. 予算感・スケジュールの希望
可能な範囲で「予算上限」「期日」などを明示することで、ベンダー各社の提案内容を比較しやすくなります。
15. 評価基準と判断フロー
「どのような基準で選定するか」「どのような提出書類が必要か」なども整理します。提案後のスケジュール感も簡単に記載しておくことで、受注側の疑問を減らすことができます。
この他にも、セキュリティ要件、保守・運用の条件、将来拡張への対応方針なども付記しておくのが望ましいです。
RFP作成を成功させるコツとよくある失敗例
RFPは発注者が一方的に「お願いごと」を書くだけの書類ではないということを理解しておく必要があります。
発注者側が主導するプロジェクトの初動ドキュメントであり、成功・失敗の分かれ道となることを忘れてはいけません。
以下では、よくある躓きポイントと、成功するための考え方・ノウハウをいくつかお伝えします。
【RFP作成で失敗しやすいケース】
• 抽象的な表現のみで、実際の運用イメージや現場課題が曖昧なまま
• 予算・納期など現実的に難しい条件を並べてしまい、受注側から良い提案が集まらない
• 社内の関係者ヒアリングを十分行わず、現場の本音が反映されていない
• RFP提出後、追加説明や質疑応答に時間が取れず、回答が雑になった
RFP作成は「準備が8割」とも言われるほど、社内関係者(現場スタッフ、経営層、情報システム部門 etc.)へのヒアリングで実際の困りごとや希望条件を集めることが重要です。現状業務の洗い出しや、実際にシステムを使っている担当者への聞き取りは現実に即したRFPを作る土台となります。
さらに、業務フロー図、既存システムの画面キャプチャ、過去の障害履歴等も添付すれば、受注側がより“自社仕様”に沿った提案を練りやすくなります。
また、「相見積もりの候補先が複数ある場合、全社に公平・同等な情報を提供する」ことも大切な視点です。不必要な情報格差や、不明点の放置は提案内容がブレる原因となるため、質問や質疑応答の窓口を設け、タイムリーかつ誠実に対応することで良質な提案が集まりやすくなります。
RFPを活用したプロジェクト推進の実例
RFPを適切に作成・活用したプロジェクトでは、どのような成果や効果が得られているのか。ここでは、いくつかの例を通じてイメージを深めましょう。
ケース1:社内の情報共有システム刷新プロジェクト
とある企業では既存の情報共有システムの老朽化に伴い刷新を決断。RFP作成前には、現行システムの問題点ヒアリングや業務フロー調査を徹底的に実施しました。その結果、既存業務の「何に困っているか」「どんな業務プロセス改善を狙うか」を明文化することができました。
RFPでは単なる“動作改善”だけでなく「ユーザーごとの権限管理」「スマートデバイス利用での利便性向上」など将来ニーズまで盛り込みました。この内容に対し、ベンダー各社は自社の強みを活かした具体的な提案を持ち寄り、最終的には従業員満足度・生産性双方が高い仕組みを導入することができました。
ケース2:受発注プロセス自動化プロジェクト
とあるメーカーでは受発注業務の手作業多発に課題を抱えていました。RFP作成段階で「どこで作業が滞るのかを現場ごとに可視化」し、具体的なボトルネックと解決すべきKPI(重要指標)を整理。将来的な事業拡張も見据えて「拡張性」や「API連携要件」にも言及しました。
これをもとに、ベンダーからは自動化ノウハウの提案やAI活用案まで広い選択肢が提示され、最終的に予算内で最大限の業務改善を達成することができました。
それぞれのケースに共通するのは、RFPによる“徹底した情報整理”が、社内関係者間やベンダーとのコミュニケーションロスを大幅に減らしていることです。
また、要件の全てを詰め切るのではなく、柔軟な質疑応答とレビューサイクルを回すことで、現実的なラインに落とし込むことができている点がポイントです。
まとめ
本記事では、RFP(提案依頼書)の基礎知識から作成の流れ、押さえるべきポイントや実用的な注意点までを解説しました。
要求事項やゴールを言語化し、情報を共有することで、複数の選択肢から最適な提案とパートナーを得るための「プロジェクト設計図」として機能するRFP。
適切なRFPはトラブルを未然に防ぐだけでなく、社内外関係者の納得と参画を促し、事業そのものの成長やイノベーションにもつながります。企業規模や業界を問わず、要件定義や発注・調達で少しでも迷いを感じているなら、まずはRFP作成からスタートしてみてはいかがでしょうか。