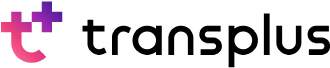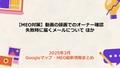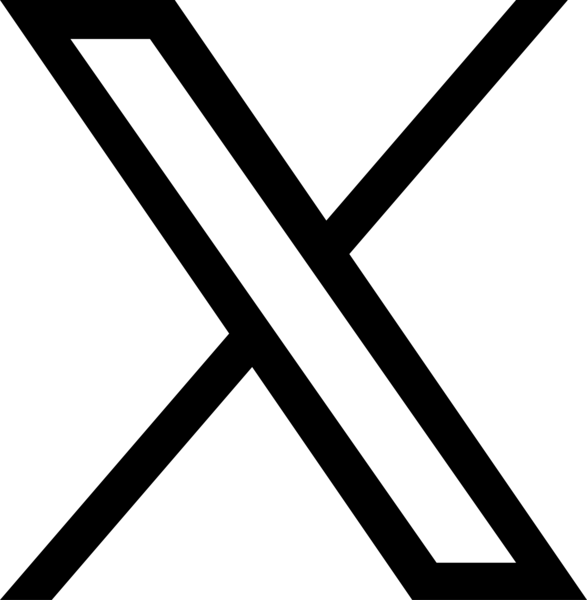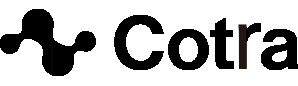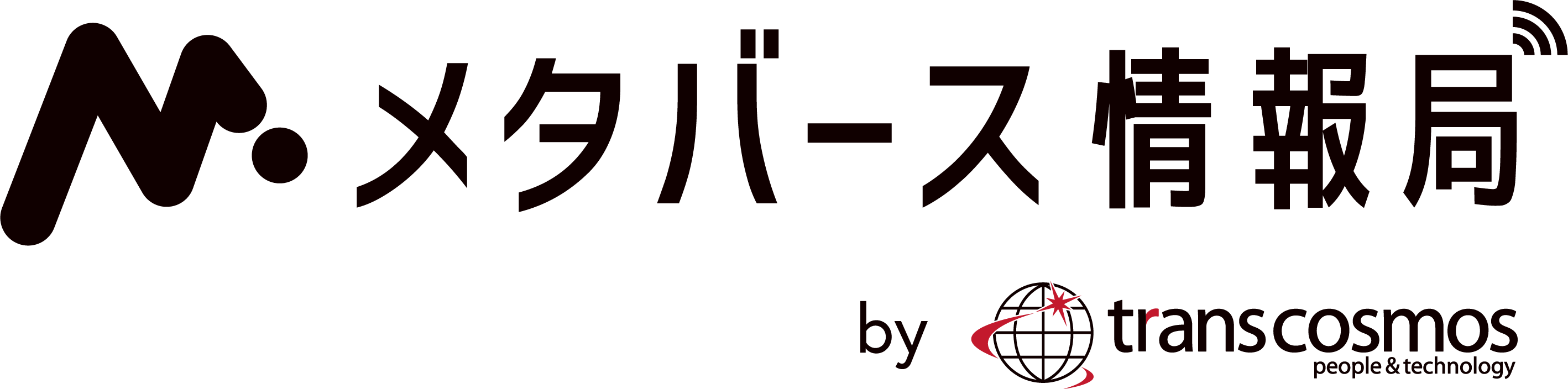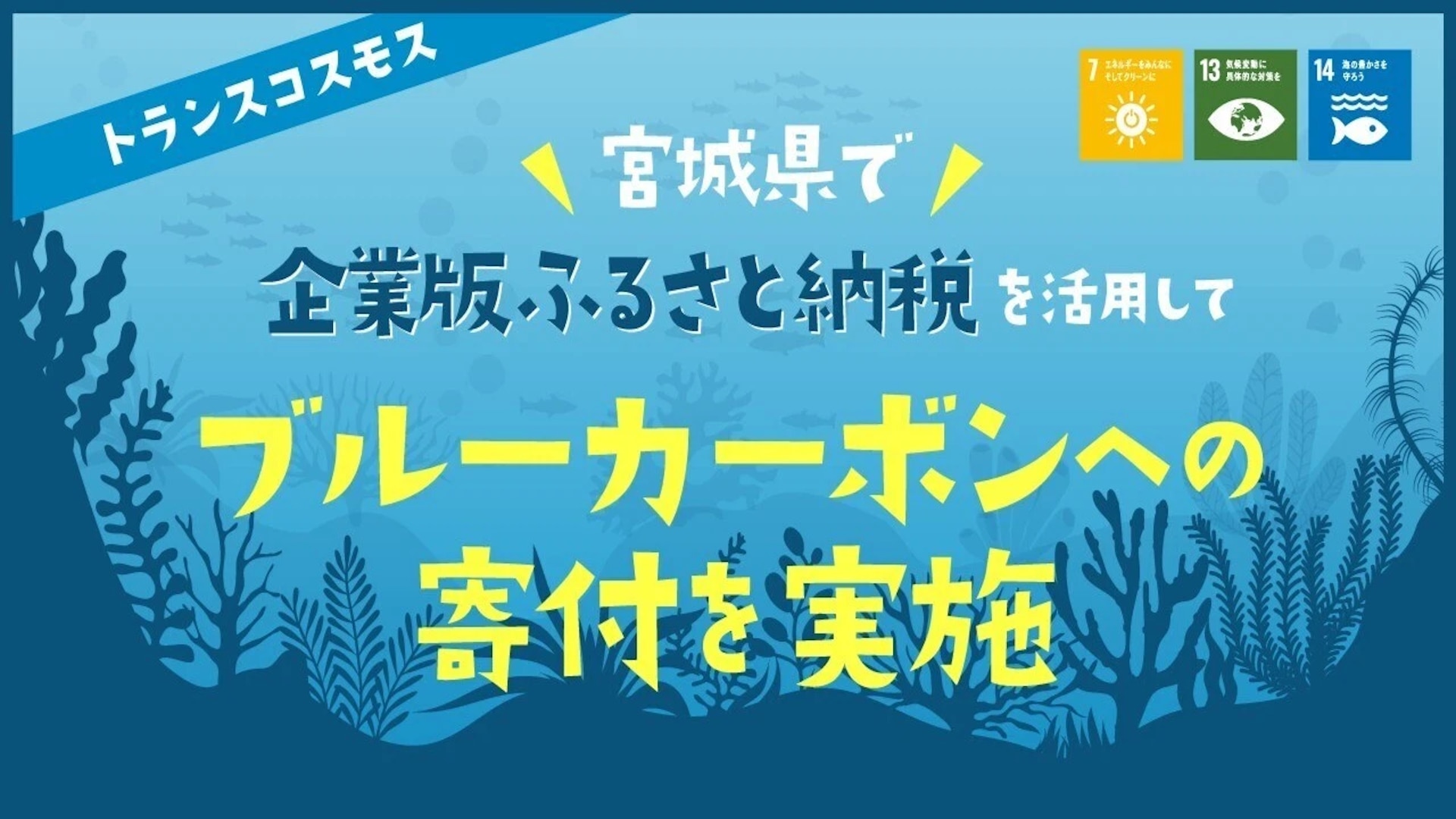
ブルーカーボン生態系を再生する「みやぎ沿岸の森づくりプロジェクト」に賛同しています!
※本記事は2025年3月19日にトランスコスモスSDGs委員会に掲載された記事を転載しています。 |
トランスコスモスは、企業版ふるさと納税制度を通じて宮城県に寄付を行いました。
今回の寄付は脱炭素・グリーン社会の実現につながる事業「みやぎ沿岸の森づくりプロジェクト」に活用される予定です。

写真左:宮城県 副知事 小林徳光(のりみつ)様
写真右:トランスコスモス 執行役員 金田浩充
みやぎ沿岸の森づくりプロジェクトについて
「みやぎ沿岸の森づくりプロジェクト」は「2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ」の目標実現に向け、海岸防災林の保育や藻場の造成・保全と海藻養殖の増産に向けた取り組みを推進し、グリーンカーボン・ブルーカーボンの両面から地球温暖化対策に取り組むことを目的に指導しました。
ブルーカーボンとは、海洋の植物や微生物がCO2を吸収し、長期にわたって海底や植物体内に炭素を蓄積する現象を指します。特に、マングローブ林、海草、海藻、干潟などの海洋や沿岸の生態系は「ブルーカーボン生態系」と呼ばれています。
ブルーカーボンは、森林などの陸上植物であるグリーンカーボンと比較して、同じ面積ならCO²吸収量に優れているとされています。ブルーカーボン生態系では、森林などの陸上の植物と同じように、光合成を通じてCO2を吸収しています。
そして、海洋生態系によって固定されたCO2は、数十年から数千年の長期間にわたって、堆積物や生態系内に保持することが可能です。こちらも陸上の植物よりも優れていると言われています。
ブルーカーボン生態系が炭素を貯蔵することで、地球温暖化を抑制することにつながるため、気候変動対策の一環として注目されています。
「みやぎ沿岸の森づくりプロジェクト」では、海岸の防災林の育成を通したグリーンカーボンの創出と同時に、海中林の造成やCO2固定量に関する研究などを進め、持続可能な漁場環境づくりを通したブルーカーボンの創出を目指しています。
ブルーカーボン生態系を守る活動が広がっています!
ブルーカーボン生態系を保護・管理する取組は、全国各地で進められています。人為的な開発や環境の悪化で減少した藻類や植物、干潟を再生させるために、人工的に植栽を行ったり保護区を設けたりする活動が行われています。
水産庁では、水産業が持つ様々な機能を最大限活用し、持続可能な開発を促進するための「水産多面的機能発揮対策」を進めています。
この取組を通じて、藻類が繁茂している場所を守るため、過密に生息したウニを駆除したり、干潟を耕して生物の生息環境を改善したりしています。
その他にも、サンゴ礁やヨシが生息する地域の保全や魚介類の放流、海洋汚染の原因になる堆積物の処理などを通じて、環境や生態系の保全が行われています。
また、「宮城ブルーカーボンプロジェクト」では、宮城県の沿岸部に広がるブルーカーボン生態系を保護・再生させ、CO2の吸収能力を高めることを目指しています。
このプロジェクトでは、2020年からモデル地区での藻場造成試験をスタート。漁港などの事業生産性と環境への影響を検証しながら、藻場造成や海藻養殖の増産を推進しています。
特徴の一つとして、地域の漁業関係者や住民との協力を重視していることが挙げられます。活動の主体である宮城県ブルーカーボン協議会は、専門家、業界、広報及び行政メンバーなどの幅広い人材で構成。地域と連携しながら、環境にやさしい水産業を実現しようとしています。
取り組みを通じて、2011年の東日本大震災の津波のために甚大な被害を受けた藻場や地域の漁業の回復、観光産業の活性化にもつながることも期待されています。
なお、「宮城ブルーカーボンプロジェクト」は、宮城県企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)での支援を受け付けています。企業版ふるさと納税については、以下の記事にてご紹介しています。
<参考>企業も活用、ふるさと納税。自治体と企業が協力し、地域活性化を目指します!
地域の経済活動とのバランスを大切に
ブルーカーボン生態系の活用は気候変動対策の一環として、ますます注目を集めています。一方で、ブルーカーボン生態系は沿岸部の環境変化や水温上昇、また海洋汚染などの影響を受けるため、地域の経済活動とバランスを取らないと効果が減少してしまう恐れもあります。
「宮城ブルーカーボンプロジェクト」の例のように、ブルーカーボン生態系は環境対策のみならず、水辺の景観やレクリエーションの場としても重要な存在です。
トランスコスモスでも、今後、ブルーカーボン生態系の保護活動を支援していく考えです。